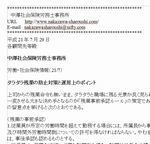少子高齢化が進み、平成22年10月1日現在で総人口に占める65歳以上の割合は23.1%になっている。今後平成32年には29.2%、平成62年には39.6%になると見込まれている。(平成23年版厚生労働白書)
これに伴い、高齢者給付費の国民所得に占める割合は昭和55年の2.5%から平成15年には15%と6倍に急増している。(高齢者給付費とは年金・老人医療・老人福祉・高年齢雇用継続給付の合計である。)また、昭和50年から始まった出生数の減少が継続し、平成17年には総人口の減少が現実化した。
以上を背景に、一律に定められていた年金支給率が昭和61年4月1日に改定され、昭和生まれの人から生年月日を追って逓減するようになった。
同時に、60歳から支給されていた厚生年金保険・共済年金が次表のように、生年月日により61歳以降となり生年月日が下る毎に支給開始が遅くなるようになった。
年金支給開始の生年月日比較
|
| 厚生年金の定額部分 | 厚生年金の報酬比例部分 |
| 男性61歳〜 | 昭和16年4月2日生まれ | 昭和28年4月2日生まれ |
| 女性61歳〜 | 昭和21年4月2日生まれ | 昭和33年4月2日生まれ |
注 共済年金は男女の差がなく男性の生年月日が適用される。
年金制度を改定する場合は既得権を尊重し、一定の年齢に達している人には古い制度を保証している。このため生年月日によって支給条件が変わることになり年金制度の判りにくい原因の一つになっている。
年金の歴史(支給率の逓減と支給開始年齢の高年齢化)相模経済新聞 2007年10月1日掲載記事