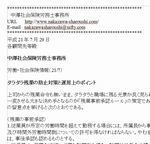年金に関することが様々な形でマスコミに取り上げられ、話題を呼んでいる。
年金には制度として加入を義務付けられている公的年金と個人が任意に加入する指摘年金とがあるが今回は公的年金に限定して説明する。
少子高齢化が進み、平成17年10月1日現在で総人口に占める65歳以上の割合は20.04%になっている。
公的年金制度には国民年金、厚生年金保険、共済年金の3つがあり加入対象者が異なる。
年金給付は、収入の減少が予見される現象が生じた場合にその保填を目的として一定の給付を行い、生活の安定を図ろうとするものである。
厚生年金保険の保険料は毎月の給与と賞与に対して1000分の146.42の率を掛けて計算する。
国民年金の保険料は収入にかかわらず毎月一定額で平成19年度は14,140円となっており、原則として毎年280円づつ引き上げられる。
年金の必要加入期間は原則として25年である。しかし、生年月日・年金の種類・性別により様々な特例がある。
期間計算には実際に保険料を納付した期間だけでなく加算される期間がある。その一つが保険料免除期間であり、もう一つがカラ期間である。
厚生年金はしばらくの間は60歳からもらえる。60歳からもらうと少なくなって損をするという話をよく聞くが、これは国民年金と混同している場合がほとんど。
前回、厚生年金保険は60歳からもらえるという話をした。6年前であればこの表現で充分であったが、現在では不充分である。
厚生年金保険の支給開始年齢について3回に渡って説明してきたが、この年齢についてはいくつかの特例がある。
国民年金(老齢基礎年金という。)のもらえる年齢は65歳である。厚生年金保険のように生年月日による差や男女による差は無いので単純でわかりやすい。
前回に引き続き国民年金の繰上げ請求のデメリットについて説明する。
厚生年金に加入した場合にどのくらいの額の年金をもらえるのか?これは年金受給者にとって一番知りたいところだと思う。
前回、厚生年金の計算式について説明したが、今回は60歳になる人の具体例で説明する。
厚生年金基金とは厚生年金とは別に、企業独自の年金を採用して福利厚生の向上を目指そうとする企業年金の一種である。
国民年金は専門用語で老齢基礎年金と呼ばれ、40年加入して792,100円の年金額になる。
老齢基礎年金の受給年齢は65歳であるが、早くもらったり(繰上げ)、遅くする(繰下げ)こともできる。
一部繰上げとは定額部分支給開始年齢までの老齢基礎年金を早くもらおうとするものである。
高年齢者等雇用安定法の改正に伴い60歳定年の会社であっても従業員が希望すれば65歳まで雇用しなければならなくなった。
厚生年金又は共済年金に加入しながら働くと年金額の調整を受けるが、その調整方法は65歳前と65歳以降で異なる。
高年齢雇用継続給付とは60歳から65歳まで雇用保険から支給される給付である。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(基本手当)を同時に受給することは出来ない。
昨年の12月から年金特別便なるものが世の中を騒がせている。
持ち主不明の年金記録が発生したもう一つの要因は手書きの記帳事務からコンピュータ化するときの作業に原因があった。
年金特別便には本人の基礎年金番号に記録されている年金加入実績のみが年金の種類別に記入される。
番外として現実に問題となっている年金特別便について3回にわたって記述したが本題に戻り障害年金について説明する。
初診日における要件とは障害の原因となった病気等の初診日において厚生年金、国民年金の被保険者でなければならない。
障害年金の金額は初診日に加入していた年金制度で大きく異なる。
1級の障害基礎年金は老齢基礎年金の満額の1.25倍で990,100円になる。
遺族年金は配偶者を失った場合に、その遺族の収入の減少を補うことを目的に支給される年金である。
遺族基礎年金は次のいずれかの者が死亡した場合に支給される。
遺族基礎年金は次のいずれをも満たした遺族に支給される。
遺族厚生年金を計算する場合、次の条件に合致した時に中高齢寡婦加算が支給される。
遺族厚生年金の計算方法は亡くなった者の年金の加入状況により、計算方法が異なる。
遺族基礎年金の額は被保険者期間や保険料納付済期間にかかわらず、定額である。
現在の年金制度では、一人一年金を原則としている
遺族給付を含んだ二つ以上の年金については、65歳前はいずれか一つの年金を選択して受給する。
お勤めしている人が退職した場合の社会保険・労働保険の手続きについて説明する。
離職票を受領後、速やかに住所地の職業安定所に出向いて申し込む。
退職時の年金の手続きは年齢や配偶者有無により異なる。
退職後は健康保険(社会保険)に加入する方法と国民健康保険に加入する方法がある。
年金のうち、老齢給付は雑所得として年金控除等を控除した残額に対し課税される。
前回は税金が徴収されることを説明したが、徴収された税金を取り戻すこともできる。
住所・受取銀行を変更する場合等には変更手続きが必要である。
年金受給者が退職したり働き始めた場合には手続きが必要である。
配偶者が年金を受給できるようになった場合には、手続きが必要な場合がある。
給与と年金、高年齢雇用継続給付を組み合わせた働き方を考慮してみよう。
当分の間、厚生年金は60歳、国民年金は65歳が本来の請求年齢である。