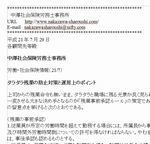これによると1970年から2009年の間の国民所得の増加額が約6倍に対し、社会保障給付費は28.2倍となっている。1990年までは国民所得額が順調に増加していた為、国民所得額に占める割合は10%前半に収まっていたが、2000年ではこの割合が20%を超え、現在では30%を超えているものと思われる。
対応策を先延ばしすれば将来的にギリシャやイタリアの二の前になりかねない危険性をはらんでいる。
支給年齢の引き上げ等年金制度全体の改定よりも不公平解消の切り口で当面の施策を考えてみたい。
第一には物価スライドの特例措置の解消である。公的年金制度では年金の受給価値の物価変動による影響を受けないよう、物価が上がった時は給付額を上げ、下がった時は引き下げるようになっている。1998年前は物価が上がり続け、年金額の増加改定を行なって来たが、1999年の物価下落時から特例法により減額改定を行わなかった年度があり、2010年度累計で2.2%にのぼっている。これは直ちに解消すべきである。1999年からの受給者はもらい得になっており、将来の受給者から見れば不公平極まりない。
第二には、第3号被保険者の制度である。サラリーマンの奥さんは保険料を負担することなく国民年金を受給できるようになっている。独身の女性から見れば、自分たちの保険料で妻帯者の妻の年金保険料を払っていることになり、不公平といえる。厚生年金保険料の引き上げや高齢者からの保険料徴収を考えるよりもまず持って不公平の解消を図るべきである。
第三には共済年金制度の脱退一時金の返戻による加入期間の復活を取りやめるべきである。
厚生年金では退職時に厚生年金を解約すると年金額増加に反映することは出来ないが、共済制度では解約したときの一時金を返戻することにより加入期間を復活することが出来る。これも制度間の不公平であり、解消すべきである。
また、重要財源に考えられている消費税の引き上げも先延ばしすればする程将来の引き上げ率が高率になり、若い世代に負担を強いるわけで、世代間の不公平を生まないよう早急に実施すべきではないか。
労働・社会保険情報(23/11)
日経ビジネスNBonline記事(23/10/31)の参照
―新しく広がるコワーキングという働き方―
今月は米国のシリコンバレーでジャーナリストとして働く加藤靖子氏の論評を紹介させていただく。
近年、サンフランシスコやニューヨークといった都市で「コワーキング・スペース」(coworking space=一緒に働く空間)が急拡大している。コワーキング・スペースとは、フリーランスのプログラマーやウェブデザイナーなど、独立して働く者同士が共有するオープンスペースのオフィスだ。
自宅を事務所とするソーホーでは、会社の事務所で見張ってくれていた上司はいなくなる。家でテレビをつけて、だらだらと時間を潰してしまうことも簡単だ。自宅作業は孤独感を感じやすく、アイディアが煮詰まることもある。しかしコワーキング・スペースでは、そうした問題を解決してくれる。オープンスペースで人とコミュニケーションを取るため、寂しくなることもない。また他人と仕事ぶりを見る事が、それぞれ個人のモチベーションになっているのだ。
自分の好きな事をやって独立していながら、コミュニティーの一部として仕事をすることが可能になる。独立しつつも人との繋がりの中で効率よく働くことが、新しいワークスタイルになっている。
サンフランシスコでウェブコンサル会社のCEOを務めるブランドン・ヒル氏が言及したメリットは3つ。
1つは、自分の職種以外の人が周りにいることで、コラボレーションが生まれること。
2つ目はコワーキング・スペースが開催するセミナーなどのイベントが、働く人の刺激になること。
3つ目は、起業家にとってコワーキング・スペースが投資家と繋がるきっかけになるということだ。
サンフランシスコやシリコンバレーは特に、投資家が流行のウェブサービスやスタートアップを積極的に探している場合が多く、コワーキングスペースを訪れるケースも多いのだ。
「今はパソコン1台で働く時代。テクノロジー系以外の職種で、例えば弁護士や会計士といった人もコワーキングで働き、コラボレーションが可能になる時代が来る」と、コワーキングがさらに広い分野で拡大していくと見通す。
日本でも東京都心を中心にコワーキング・スペースの利用が急速に進みつつある。地元相模原の「さがみはら産業創造センター」でレンタルスペースとして提供しているシェアードオフイス「Desk10」の利用も増加しているとの中村部長の話である。「Desk10」は一部屋に10人分の専用机があり、ワークデスク、コピー・プリンターの複合機、シュレッダーを共用できるようになっている。
1ヶ月の基本料金は8,400円で、希望により、住所使用8,400円、専用ロッカー1,890円、電話代行13,230円で選択利用が出来る。自前の事務所を開設するのに比較すればリーズナブルな費用で事務所を開設できる。(「さがみはら産業創造センター」HP:http://www.sic-sagamihara.jp/)
また米国の新しいトレンドとして、母親もしくは父親が働くコワーキング・スペースで、子供も預けられるサービスを提供している所がある。2つのサービスを組み合わせることで、借り手は割引を受け、コストを削減することができる。自分の職場近くに子供を預けられるため、安心して働く事ができるというメリットも大きい。
労働・社会保険情報(23/10)
―年金夫婦分割案について―
9月29日に夫の厚生年金を夫婦に2等分する案が厚生労働省の方針として報道された。
現在の年金制度では、サラリーマン所帯で妻が専業主婦である場合、夫は老齢基礎年金に厚生年金(共済年金の場合は共済年金、以下同じ)が加算された年金を受け取り、妻は夫の厚生年金から拠出された保険料に基づく老齢基礎年金を受け取るようになっている。
昭和61年3月以前の年金制度(旧法の年金制度)では妻の年金権が確立されておらず、妻に年金加入の義務がなかった。妻は夫の年金で養ってもらえば良いとの考え方が支配的な時代であったからである。女性の地位向上に伴って、昭和61年4月から年金制度が大幅に変わり(新年金制度)、サラリーマンの妻も国民年金に加入して65歳から老齢基礎年金を受給できるようになった。しかし、その制度の内容は、妻に収入がないとの理由から妻の年金に見あう保険料を徴収せず、厚生年金の加入者全体で、保険料を負担する内容にしたのである。そのため、機会ある毎に独身者から不公平な制度であるという不満が寄せられていた。
今回の厚生労働省案は妻も家事で夫の稼ぎに貢献しているのであるから、夫の支払った保険料の半分は妻の払った保険料であるとみなし、夫の老齢厚生年金を2等分して妻の年金にしようとするものである。結果として夫婦平等の年金を受け取るようになる。妻が保険料負担無しに年金を受け取れるという不満に対し、妻も保険料を負担しているという考え方を打ち出したわけである。 専業主婦がいる世帯の家計の中だけで見ればある程度理解できる案ではあるが、独身世帯との比較では、同じ保険料で専業主婦のいる世帯は二人分の老齢基礎年金を受け取るのであるから不公平は解消しない。
今回の案に対し、
○ 夫婦の年齢差、特に妻の年齢が夫より若い場合の受給時期の差による損失。
○ 夫が亡くなった場合、妻が遺族年金(通常夫の老齢厚生年金の4分の3)を受け取れないので損する。
等の問題も指摘されているが根本的な不公平を解消することが重要であると考える。
国民健康保険の制度では保険料が収入による分と世帯割り、人数割りがあり、独身世帯と扶養家族がある世帯では保険料に大きな差がつくようになっている。厚生年金・健康保険の保険料でもこのような考え方を導入すべきではないか。
高齢化で年金財政の解決が問題になっている訳であるが、その解決策の一つとして、専業主婦からの保険料徴収と健康保険における扶養家族の分の保険料徴収を検討すべきである。急速な負担増に対しては税制等の対応を図ることも検討課題になるとは思うが。また、パートタイマーに対して社会保険を適用する案も検討されているが、一般社員の労働時間あるいは労働日数の4分の3未満で働く社会保険の加入義務がない短時間労働者を多く抱える事業所の負担増は無視できず、年金保険料率の自動的アップと相まって強制適用事業所自体の社会保険未加入が益々増えてしまう原因になるのではないかと危惧するものである。